肌にのせる⾊、⼼に残るもの。
化学染料と⾃然染料のあいだで
いつの頃からか、
私たちは“安くて扱いやすいもの”を
選ぶようになりました。

化学染料で染められた鮮やかな⾊、
化学繊維でつくられた服

それらは⼿軽で、効率的で、
そしてどこか“安⼼”に⾒えるものだったのかもしれません。
でも今、ふと⽴ち⽌まって感じる⼈が増えています。
この服は、本当に⾃分の⾝体にやさしいだろうか。
この⾊は、どこから来て、どこへ還るのだろうか。

〈写真・京都、二条城キーファー展〉
化学染料は、現代の⾐服を⽀える⼤きな柱です。
鮮やかで安定し、量産に向いており、⾊落ちも少ない。
けれど、その便利さの裏で
肌に直接ふれる私たちの体への影響や、
染⾊に携わる⼈々の健康被害も指摘されています。

たとえば、化学染料を扱う現場では、
アレルギーや⽪膚疾患、呼吸器への負担などの
リスクが伴うこともある。
そしてその影響は、「着る⼈」だけでなく、
「つくる⼈」や「⼟や⽔」**にも広がっています。
fumika では、植物染料を⼤切にしています。
それはただ「⾃然だから」ではなく、
“⾃然にしか出せない美しさ”があるからです。

草⽊や花、果⽪や⼟
⾃然のあらゆるものから⾊をいただいた布には、
どれも微妙に異なる⾊合いがあります。

〈写真・浜離宮恩賜公園の桜〉
まったく同じ⾊は、
ひとつとして存在しない。
それは⼈間と同じように、
唯⼀無⼆の存在であり、
だからこそ、その不均質な揺らぎや濃淡に、
私たちは静かに⼼を動かされるのかもしれません。

〈写真・泥で染められた大島紬〉
天然素材(絹・⿇・⽊綿・⽺⽑など)は、
草⽊染めと深く調和します。
肌に触れたときに感じる軽さや通気性、
そして呼吸するような着⼼地。

〈写真・大島紬のセットアップ〉
たとえば絹は、冬は暖かく、夏は涼しい
⾃然の理にかなった布です。
けれど今、なぜこの⼼地よさを
「知らない」⼈が多いのか。
それは、育った環境にあるのかもしれません。
たとえば親が選んだ安価な服、
化学繊維中⼼の暮らし。
「それしか知らなかった」からこそ、
違和感にも気づきにくい。
けれど、肌や体は、じつはずっと覚えている。

〈写真・紬のジャケット〉
⾃分の⾝体に合わないものを、
静かに知らせてくれることもあるのです。
今、化学に囲まれた世界だからこそ、
あらためて⾃然の⾊・天然素材
⼿しごとに惹かれる⼈が増えています。

〈写真・東京・汐留のアトリエにて〉
それはただの“ノスタルジー”ではなく、
「知ること」から始まる選択の⼀歩です。
fumika では、植物染料による染⾊や、
天然素材の⼿ざわりを尊び、
そこに込められた時間や記憶、
そして魂を再び纏いなおすことを⽬指しています。

〈写真・東京・汐留の小さなアトリエ〉
化学が悪で、⾃然が正義という話ではありません。
けれど⼀度、⾃分の体と⼼が何を求めているのか、
静かに⽿を澄ましてみること。
それが、“装うこと”の本質かもしれません。

〈写真・ぼかし染の紬ジャケット〉
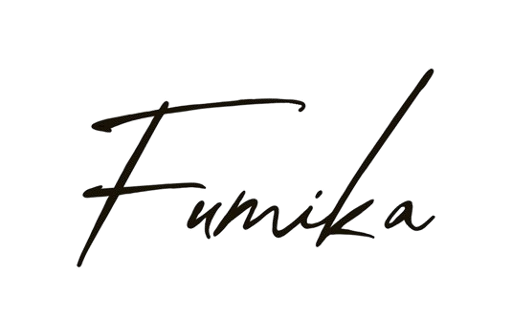
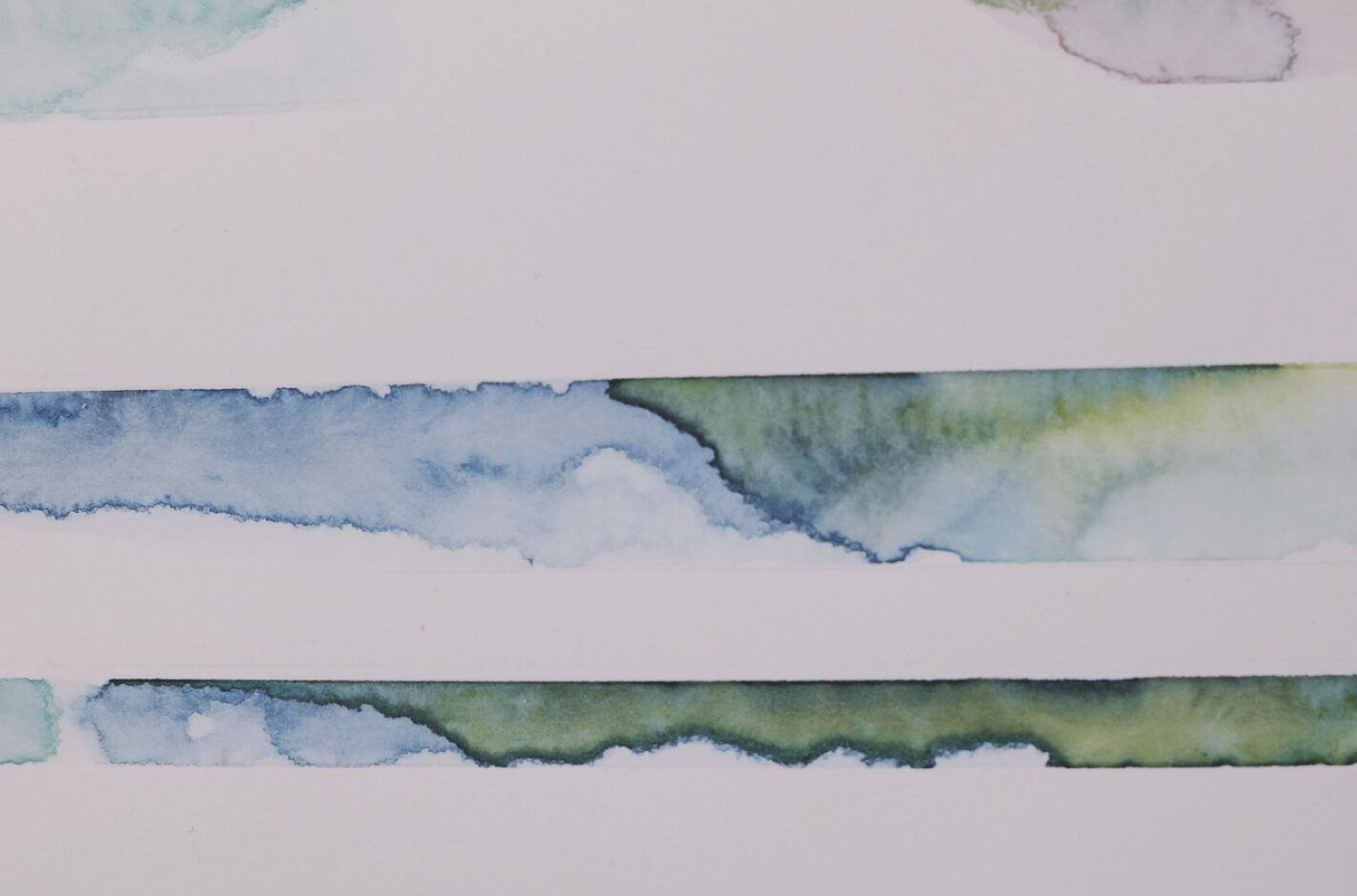






コメント
この記事へのコメントはありません。